皆さん、こんにちは!
リンクトゥミャンマー・インターンの下畑です。
本日は8月に開催されたかながわコミュニティカレッジの活動報告をしたいと思います。
活動内容
かながわコミュニティカレッジ連携講座『在日ミャンマー人支援の現場から見つける、私たちの多文化共生社会』が、8月に全4回開催され、受講者はボランティアも含めて全16人と、非常に多くの方に参加していただきました。
第1回目と第2回目は講義形式で、ミャンマーという国や政治状況にまつわる解説、またリンクトゥミャンマーが行っている支援事業を紹介しました。支援事業に関しては、外国人が日本で生活する際に直面する問題やそういった在日外国人を支援する際に意識している点を、ミャンマー人支援を多く行ってきたスタッフの体験談を交えながら説明しました。

ミャンマー人の定住支援について説明する様子
難民申請のプロセスを理解する
前半の講義形式から打って変わって、後半となる3回目と4回目ではグループワークを中心に講座が進められました。第3回では「難民申請のシミュレーション」を受講者の方に体験していただきました。
「日本の難民申請は難しい、認定されづらい」とよく言われますが、実際にどのようなプロセスを経ているのか、理解している人は多くはありません。そこで、難民申請のプロセスを理解するために、難民申請者とその支援者チーム、入管の審査部門担当者・法務大臣チームに分かれ、それぞれの観点からディスカッションをするというグループワークを行いました。難民申請側は「難民認定してもらうためには、どのような証拠・資料が必要か」といった観点で、入管側は「その人は難民であると認められるだろうか」といった観点でディスカッションを進めます。
グループワークでは、難民申請チームが、自身が自国で迫害を受ける恐れがあることを客観的に示す証拠を提示することに苦労していた印象があります。どんな活動にいつ参加していたのか、具体的にどんな危険が迫っているのか、身近に危険な目にあった人がいるのかなどを行政が確認できるレベルの証拠で示さなければいけません。グループワークを通して、難民認定の難しさをみなさまと共有できたと思います。
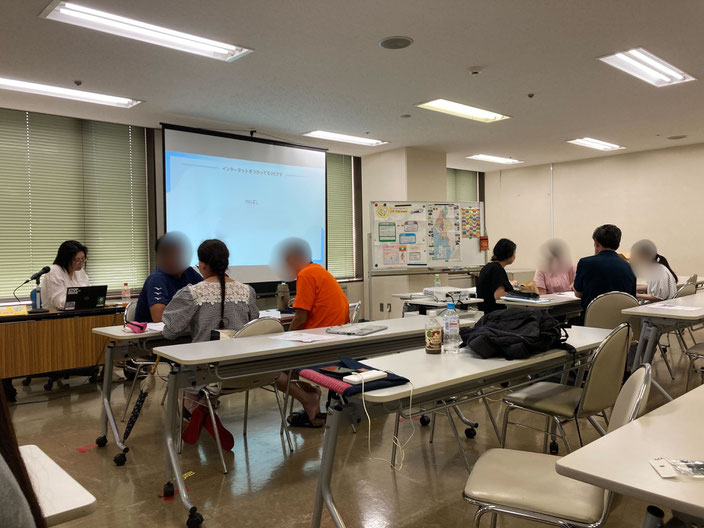
第3回のグループワークの様子
外国人と共生していくうえで起こりうる問題について考える
4回目では、外国人と共生していくうえで起こりうる架空の問題を設定し、それに対してどのように解決したらいいか話し合うというグループワークを行いました。ディスカッションであげられた設定は、
- 隣の部屋の外国人の料理のにおいが気になる
- 外国人を積極的に雇っていることを取り上げた記事に対して批判的なコメントが多く寄せられた
- 外国人の児童が学校でいじめにあっている
- 複数の国の外国人が働いている企業で、外国人同士の対立が起きた
の4つ。どれも解決方法を考えるのは難しく、参加者からも「いい方法が思いつかなかった」という声が多く上がりました。
実際に外国人が同じ職場にいたり、近所に住んでいたりすることでどうしてもトラブルが発生してしまうということは多くあります。しかし、その際に100%日本のやり方や自分の主張を通すのではなく、彼ら/彼女らと話し合いお互いに納得できるポイントを見つけることが重要です。そのことを参加者の方とともに考えることができたのではないかと思います。

第4回のグループワークの様子
参加した感想
全4回の講座に参加し、ミャンマーについてや難民や外国人が日本で直面する問題について理解することができました。特に、第4回目で行ったグループワークで、「隣の部屋の外国人の料理のにおいが気になる」という問題の解決方法を議論したのが、私の中でとても印象に残っています。
料理のにおいが気になったとしても、何を食べるかはその人の自由なので、料理を作らないようお願いしたり、作る回数を減らすようお願いするのは難しいのではないかという意見が出ました。また、管理会社や大家に相談するという意見が出た一方で、誰かに問題解決を任せてしまうと住人同士の溝が深まるのではないかという意見もありました。
このように正解が一つではないからこそ、自分の意見を押しつけずに柔軟に対応していくことが必要だと学びました。
最後に
最後まで読んでくださり、ありがとうございました!
リンクトゥミャンマーでは、11/29(土)に富岡総合公園で、11/30(日)に金沢公会堂で行われる国際交流イベントに参加し、ミャンマーコーヒーなどを販売する予定です。
リンクトゥミャンマーの活動や国際交流に興味のある方は、ぜひご参加ください!
